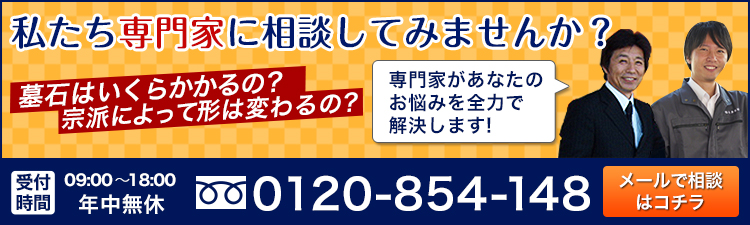法要・供養について1

法要・供養の基礎知識
法要・供養の基礎知識として、開眼供養から墓所整理に至る流れを、仏式を中心に説明します。
開眼供養(かいがんくよう)
 墓所に仏様が埋葬されている、いないに関係なく、お墓は大切な先祖
墓所に仏様が埋葬されている、いないに関係なく、お墓は大切な先祖供養の対象になります。最近では、埋葬時に一緒に行うことが多いで
すが、墓石はご住職にお経を唱えて頂いて、はじめて「信仰礼拝の対象
として本当の意味の“墓石”」となります。開眼供養は、入魂式(にゅう
こんしき)とも言われ、儀式を経ることで、お墓に限らず、仏像や仏壇、
仏画、卒都婆、位牌などが霊験ある存在になります。つまり、魂を入れ
ない墓石はただの石にすぎず、開眼(入魂)のお経を唱えていただき、
魂を入れることでご先祖さまとの絆が生まれます。なお、法要の営み方については、宗派によってことなります
ので、菩提寺に事前にご相談されることをお勧めします。法要・供養の基礎知識として、開眼供養から墓所
整理に至る流れを、仏式を中心に説明します。
追善法要・年忌法要
 仏教では、より良い死後の世界に行き着くようにとの願いから、
仏教では、より良い死後の世界に行き着くようにとの願いから、亡くなられた日を含めて七日目ごとの法要(中陰供養)と「百箇日
忌法要」「毎月の命日」「新盆」などの追善法要を営みます。百箇日
を過ぎると年忌法要となり、満一年たった祥月命日が「一周忌」、
二年目が「三回忌」、以後は数え年で六年目に「七回忌」、「十三回忌」
「十七回忌」「二十三回忌」「二十七回忌」「三十三回忌」「三十七回忌」
「四十三回忌」「四十七回忌」「五十回忌」「百回忌」と続きます。
先祖供養として欠くことのできない大切な行事である、これらの法要は、近親者を招いてお寺や墓前で
営みます。また、残された者の大事なつとめとして、春秋のお彼岸やお盆には、家族揃って墓参し、個人を
偲び供養します。
納骨供養
 亡くなられたあとの四十九日間をこの世とあの世の中間の世界とし
亡くなられたあとの四十九日間をこの世とあの世の中間の世界とし中陰といいます。通常、忌明けの中陰を過ぎてから、遺骨をお墓に
納める「納骨法要」を営みます。